最近の新しい電源ユニットを知ろう
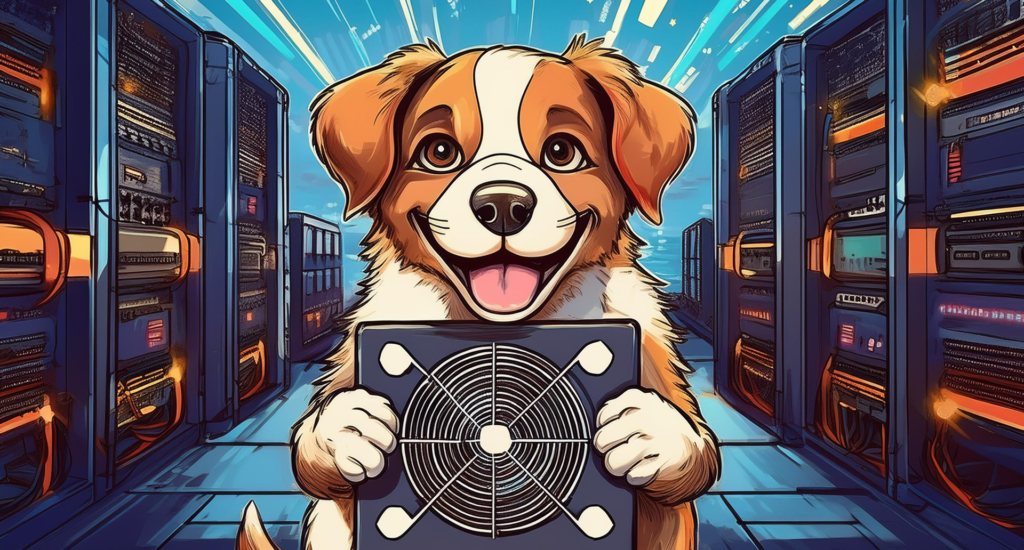
近年のハイエンドGPUや構成のCPUへの対応を見据え、ATX電源ユニットの規格も進化し続けています。その最新規格として注目されているのがATX3.1。この記事では、ATX3.1電源が従来規格(ATX2.xや3.0)とどう異なるのか、具体的なメリットや構成要件などを解説します。
当サイトにはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。
当サイトの広告掲載ポリシー(https://nanimono-pc.com/ad-policy/)
ATX規格とは
電源ユニットにおけるATX規格とは、PC電源ユニットの形状やコネクタ仕様などを定めた標準です。ATX 2.xが長年にわたり普及していましたが、近年のGPUの大電力化やCPUのピーク電力増に合わせて規格が改定され、ATX3.0 / 3.1へと進化しました。
ATX 2.x
登場時期
2000年代初頭から普及し、長年にわたって標準的な電源ユニットとして定着。
主な特徴
- メイン電源コネクタは24ピン(一部初期は20ピン)
- CPU補助電源として4ピン(後に8ピンも)
- PCIe補助電源(6ピン / 8ピン)を別途追加してGPUに対応
制限
- 高性能GPUが登場するにつれ、急激なピーク電力や600W級の大電力を供給する想定は薄かった。
- 電圧レギュレーションや保護機能が、現在のハイエンド環境には十分でない場合もある。
ATX 3.0
登場背景
RTX30シリーズ以降のGPUが求める大電力(数百W~600W級)に対応するため。
主な変更点
- あらたに12ピン+4ピン(12VHPWR)コネクタを導入。1本のケーブルで最大600Wを供給可能
- ピーク電力対応:短時間で定格の2倍近い急激な電力変動に耐える設計が推奨
- 電圧レギュレーションや効率向上が強化
メリット
- ケーブル本数が減り、配線がすっきりする
- ハイエンドGPU向けに変換アダプタ不要の製品が増加している
ATX 3.1
さらなる改良
- ATX 3.0で導入された機能を洗練し、安定供給・効率・保護機能を強化
- 12VHPWRコネクタ周辺の仕様を最適化し、ハイエンドGPUへの対応をより確実に
ピーク電力への耐性
120%~200%の急激なピーク負荷に対する想定が標準化され、ゲームやクリエイティブ用途の高負荷でも安定
高品質コンポーネントの使用
コンデンサや回路設計が一層厳格に。寿命・安全性も向上
ATX 3.1の主な特徴
12VHPWRから12V-2×6(16-pin)への移行

ATX 3.0で採用された12VHPWRコネクタは、一時期の呼称として定着していましたが、最近では12-2×6(16-pin)と呼ばれる名称へ移行しつつあります。これは、12本の電力線+4本の信号線を組み合わせた合計16ピンの仕様で、最大600Wの大電力を1本のケーブルで供給可能です。
なぜ名称が変わるのか
PCI-SIGの最新ガイドラインでは12VHPWRをより明確に定義するため、12V-2×6という新しい呼称を使う動きが進んでいます。
両方とも互換性はあるのですが、接触不良や熱問題に対する強化がされています。
ピーク電力への対応強化
ハイエンドGPUや最新のCPUは、一瞬だけ大きな電力を要求するピーク(突入電力)があります。ATX 3.1では、120%~200%の急激なピーク電力に耐えることを前提に設計がなされています。これにより、ゲームやレンダリングなど急激な負荷変動にも安定して対応可能です。
電圧レギュレーションと効率向上
電圧レギュレーション(±〇%以内に抑える)が従来より厳格化され、大きな負荷変動でも12Vラインを安定供給できるようになりました。これに伴って、効率面でもさらなる改善が期待されます。
寿命と安全性の向上
高品質コンデンサや回路設計を前提とするため、結果的に電源ユニット自体の耐久性も向上。過電流保護(OCP)や過電圧保護(OVP)などの保護回路も前提として強化されている傾向にあります。
ATX 3.1電源を選ぶメリット
ハイエンドGPUに対応しやすい
RTX40シリーズや50シリーズなどのハイエンドモデルに必要な大電力を余裕をもって供給します。また、最近発売となった5090や5080は、その消費電力の多さからより発熱しやすくなっていると考えられます。その対策としてより良い電源を選ぶことが必要になってきました。なので、5090、5080ではATX 3.1がほぼ必須といっても過言ではないでしょう。
将来的な拡張性
最新規格のため、PCを長期間使う際も安心。次世代GPUやCPUへの対応も見込めます。
安定供給でパフォーマンス向上
負荷変動の激しい場面(ゲーム中の高FPS・動画エンコードなど)でも電圧ドロップが起きにくく安定します。また、それによってシステム全体のパフォーマンスを引き出しやすくなっています。
電圧ドロップが起きにくいことのメリット
- ゲームなど高負荷状態の急激な電力変動でも、システム全体が安定稼働
- FPS(フレームレート)の安定や動画エンコード速度の向上など、パフォーマンスに好影響
- パーツに十分な電力が供給されるため、誤動作やクラッシュのリスクを低減
効率と寿命の両立
電力ロスが減り、発熱も少ない設計が期待できるため、長期的なコストや冷却面も有利となっています。
選ぶ際の注意点
対応W数を確認
600Wの12V-2×6を使う場合でも、電源ユニットの合計W数が750Wや850Wなど適切に余裕があるかチェックしましょう。
コネクタの実装
12V-2×6コネクタ以外に、従来の8ピン補助電源がいくつ必要かも確認しましょう(レガシーGPUや拡張カードがある場合)。
ケーブルの品質
- 付属ケーブルの太さや素材をチェック。ハイエンドGPUへの大電流供給では、線径が不足すると発熱リスクが高まる
- 12V-2×6ケーブルが付属しているか、そしてそのケーブルが推奨される「曲げ半径」「定格アンペア数」を満たしているか確認
- コネクタ部分(例えば12V-2×6のロック機構など)がしっかりした設計かどうか。抜けやすい・緩みにくい仕様を選ぶと安全
- 個別スリーブケーブル(1本1本が独立スリーブで保護されているタイプ)だと、エアフローや美観が向上。ただし、取り回しはやや難しい
線径(ゲージ)
一般的に「16AWG」や「18AWG」などの表記で線の太さを示します。ハイパワー用には16AWGのように太いケーブルが望ましく、18AWG以下だと大電力供給時に発熱しやすいです。
曲げ半径
12V-2×6ケーブルは、コネクタ近くを強く曲げると接触不良やコネクタのゆるみの原因になります。電源メーカーやGPUメーカーが推奨する「ケーブルを曲げ始める位置」を守ることが大切です。
スリーブ(被膜)素材
たとえばナイロンメッシュ(パラコード)やPETスリーブなどの、耐熱・耐摩耗に強い素材が好ましいです。
予算とコスパのバランス
ATX 3.1電源は高価なモデルばかりになっています。そのため予算とコストパフォーマンスとのバランスをちゃんと考慮して選ぶようにしましょう。
スペックの高いものを選択肢として与えられると、どうしても高スペックのものを選びたくなってしまいがちです。本当に必要かどうかちゃんと吟味しましょう。
まとめ
ATX 3.1規格の電源ユニットは、高いピーク電力や12V-2×6(16-pin)コネクタへの対応を前提に設計されており、ハイエンド志向の自作PCや将来的な拡張を考えているユーザーにとって大きなメリットがあります。
- 大電力GPUへの対応
- 安定した電圧供給
- 将来の規格変更にも柔軟に対応
価格やモデル数はまだ多くないものの、長く使える電源を求めるならATX 3.1を検討する価値は十分にあるでしょう。そのため、現時点でハイエンドGPUを視野に入れているなら、積極的に選択肢に入れてみてください。

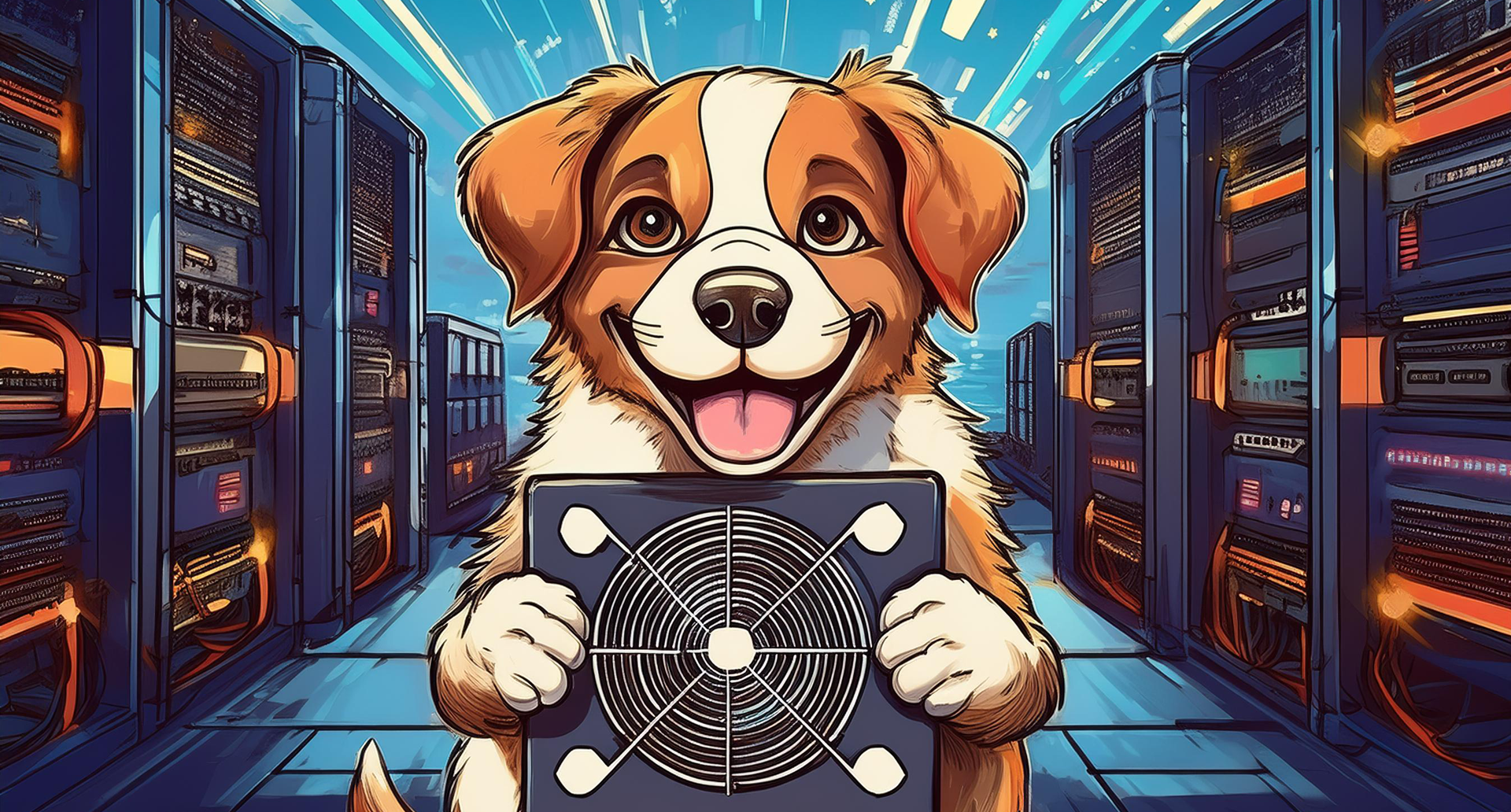

コメント